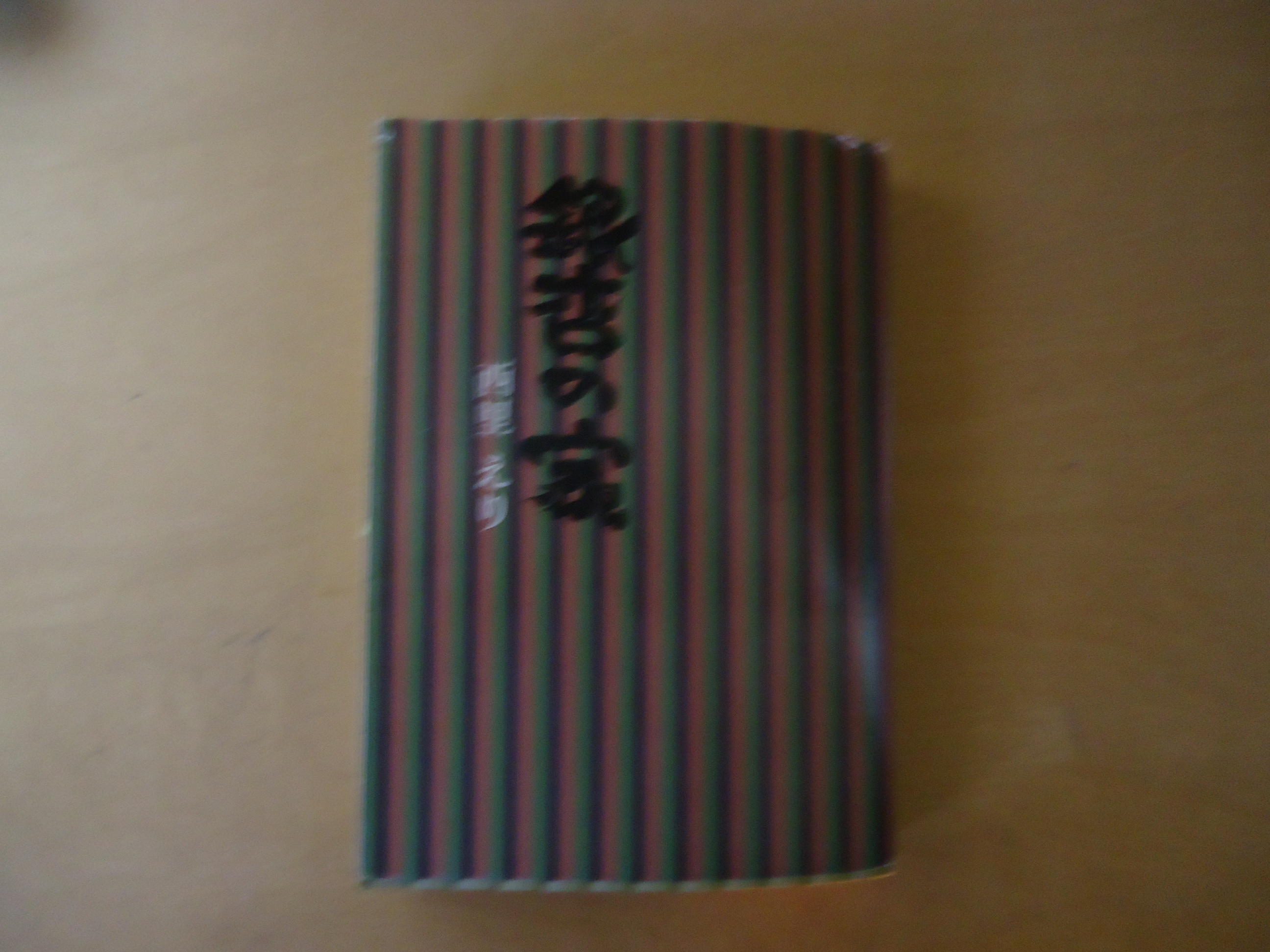 西里えり著・「銀杏の家」
西里えり著・「銀杏の家」の序文は
「明治の歌人・長塚節に「土」という農民小説の名作がある。この作品を朝日新聞に推せんした夏目漱石は、「この作品を読むことは、多くの人々にとって苦痛であろう。苦痛だからなおさら読んでほしいと思う。東京の近くに、現在このような人々が生きて暮らしていることを、多くの人に知って頂きたいと思う」というような意味のことを述べている。
西里さんのこの小説は、「土」に劣らないくらい、よく書かれた作品なのではないかと私は思っている。大陸から引き揚げて、三人の子どもをかかえた若い女性が、金津近郊の農村に腰をすえて、きびしい生活をとおして、次第にその農村にとけ込んで行く過程が、きわめて自然に、かつ克明に、よく描かれていると思う。
夏目漱石は「土」を読むことは苦痛だと言ったが、現代の読者がこの作品を読むことがそれほど苦痛とは思われない。それは小説の技巧が、長塚節より優れているという意味ではない。ここには農村における娯楽や、ちょっとしたラブアフェアも描かれてはいるが、そのためだけでもない。一番大きな相違は、明治時代の農村と、戦後の農村との舞台の差であろう。前者が全く暗い、救いのないものであったのに対し、後者には、やはり暗いところもあるが、明るい展望も開きかけていて、読者に希望を抱かせるものがある。この差異は大きいし、我々はそれを大事にして行かなければならないと思う。
もちろん現代の農村に、新たな問題が発生していることを知らないわけではないが、この小説はそれには触れていないし、また触れる必要もなかったと思う。読者は巻を閉じてから、ゆっくりと現実の問題に思いをめぐらされるのもよいであろう。
この作品は、作者の母を主なモデルとしていると伺っている。もちろん事実そのままではなく、いろいろなフィクションがあることと思うが、戦後の困難な時期をけんめいに生きた女性の面影は、ありありと描かれているし、そのイメージは永く読者の脳裏に定着するのではなかろうか。その意味で、亡き母に対する鎮魂の思いは、十分果たされたとしてよいと思われる。
この作品が、本県文学の中で近来稀な秀作の一つとして、広く江湖に迎えられることを願ってやまない。
1996年9月9日 白崎昭一郎」
と書かれている。
「銀杏の家」は二度目なのだが、前回は序文を読むのを忘れていたので、けんめいにキーボードを叩いてここにアップした。
ところで
昨日の来訪者から、「まきちゃんのブログ文章には味がある」と言われた。男性から誉められたのは二人目なので嬉しかったのだが、考えてみると、私の人生は浮気の連続だった。
20代の頃は線引きに熱中し、30代に入ってから手話に夢中になり、40を過ぎた頃から小説が好きになり、40代後半に議員となってからは市民に嫌われないように仮面をかぶって生きてきた。
6月からの私は、好きな歴史路を散策し好きな小説を読み好きな仕事にいそしみ時折一人旅を楽しむ日々を送りたい。

